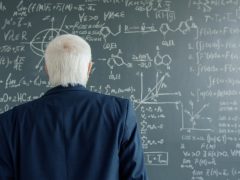ウサギを追う人、鹿を待つ人
 ルソーの「鹿狩りの寓話」は、人間の協力と信頼のあり方を象徴しています。複数の人が協力すれば、大きな利益が得られる鹿を狩ることができる。けれども、その協力が成立するには、お互いを信じ、待つことが必要です。ところが、仲間を信じきれない者が、目の前に現れたウサギを追ってしまう。結果、鹿は逃げ、皆が失う。この寓話は、社会の意思決定や組織の行動にも通じるものがあります。
ルソーの「鹿狩りの寓話」は、人間の協力と信頼のあり方を象徴しています。複数の人が協力すれば、大きな利益が得られる鹿を狩ることができる。けれども、その協力が成立するには、お互いを信じ、待つことが必要です。ところが、仲間を信じきれない者が、目の前に現れたウサギを追ってしまう。結果、鹿は逃げ、皆が失う。この寓話は、社会の意思決定や組織の行動にも通じるものがあります。
多くの人はこの物語を「理性的に協力することの大切さ」と読みます。ここでの理性とは、本能に流されず、互いに協力する知恵のことです。しかし、私がここで使う理性という言葉は、もう少し異なる意味を持ちます。それは、論理的・合理的に判断し、数値化できる確実性を優先する思考です。
理性的な人は、未来を予測し、効率や成果を重視します。その力は社会の発展を支えてきました。しかし、現代ではその理性が、制度や経済の仕組みの中で「短期化」しています。株主至上主義や四半期決算、即時評価といったシステムが、長期的な価値よりも短期的な成果を優先するよう促しているのです。本来、理性は未来を描くための力であったはずなのに、いまは「すぐ結果を出すための合理性」へと押し込められてしまっている。
一方、感性の人は、時間を線としてではなく「場」として感じ取ります。数字にならない気配や流れを察し、全体の調和の中で動く。森の静けさ、仲間の息づかい、鹿が現れる気配。そうしたすべてをひとつのリズムとして受け取りながら行動する。感性にとって「待つ」とは、何もしないことではなく、世界の流れに耳を澄ませながら、自分の動きを合わせる能動的な行為なのです。
理性が分析によって未来を描くなら、感性はつながりの中で未来を感じ取る。どちらが優れているということではなく、理性が切り分けた世界に、感性がもう一度「全体」を取り戻すのです。
現代社会は、理性の成果によって繁栄してきました。けれども、その理性が環境や人間の心のリズムから乖離しはじめている。ウサギを追う速さばかりが増しても、鹿がどこにいるのか、森の気配そのものを感じ取れなくなっているのです。
いま私たちに求められているのは、理性を否定することではなく、理性の中に感性を取り戻すことです。すばやく動きながらも、全体の流れを感じ取ること。それが、ウサギを追いながら鹿の気配を感じる生き方です。