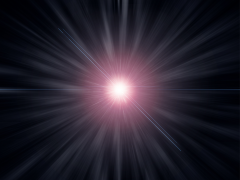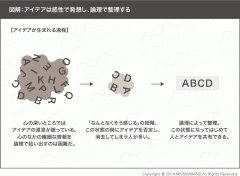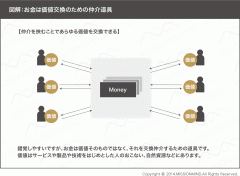感性の網
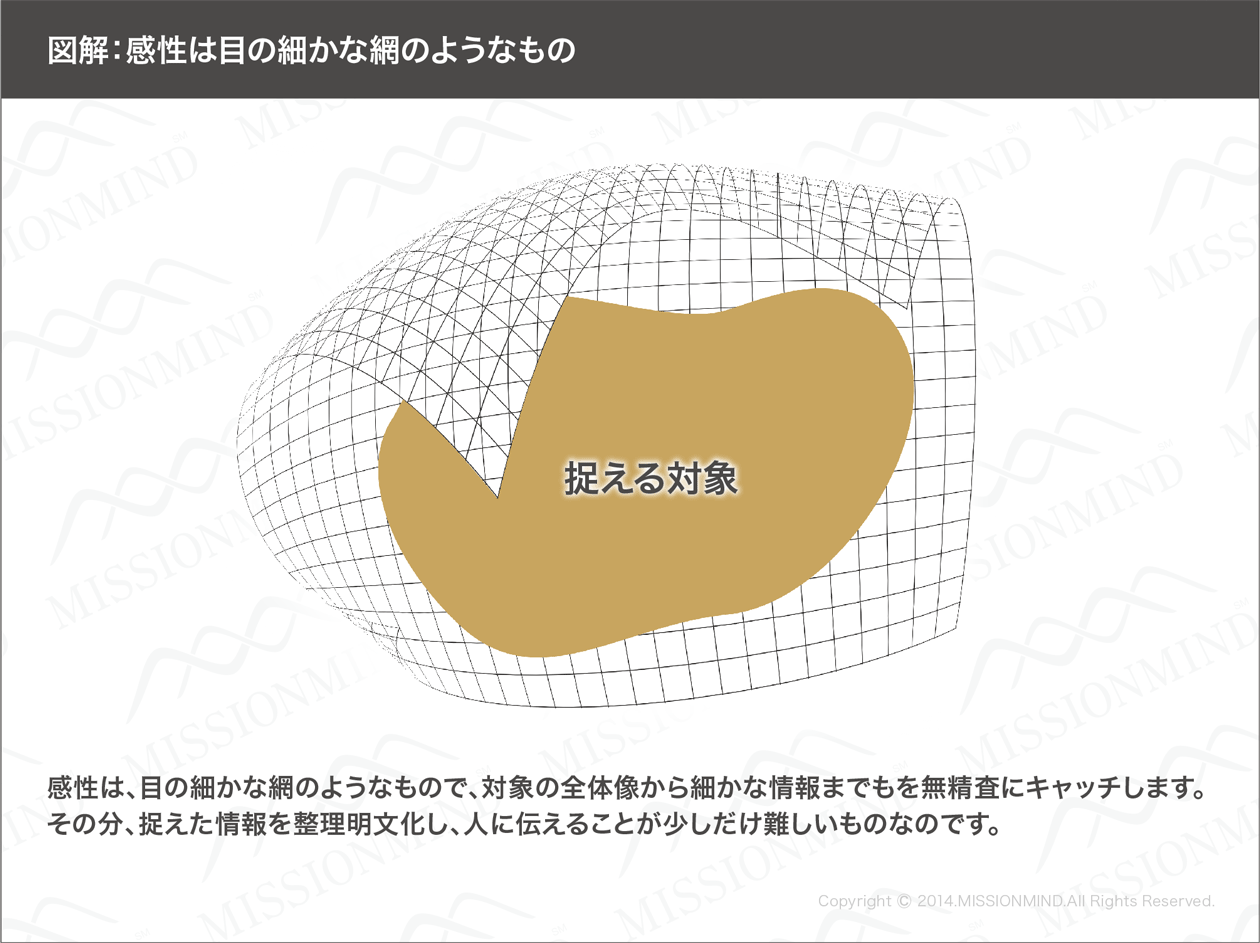
日常社会で生きている中で「何か引っ掛かる」や「理由はわからないけどこうした方がいい気がする」など、私たちは明文化できないまでも様々な考えを抱くことがあります。ただ、その考えを聞いた時に他の人は、当然「理由は?どうしてそう思うの?」と聞いてくるでしょう。しかし、感性で捉えたものは、当人の印象からくるものが多く、その理由を説明できない事も少なくありません。こうした時に、大概にして人の納得を得られず、当初の考えを捨てて論理的に筋の通った理性的な別の考えに、不本意ながらも従うということが多くされてきています。と言っても、論理的で理性的な考えを、否定するわけではありません。ただ、「理由を説明できる」ということに価値基準を置きすぎていることが問題のように思うことが度々あるのです。
感性をこの記事であえて例えるならば、「目の細かな網」のようなものと言えます。対象の全体像から、実に細かな情報までもを無精査にキャッチしますが、その分捉えた情報を整理明文化し、人に伝えることが少しだけ難しいものなのです。逆に理性は、釣り針のようなもので、ピンポイントに主題の細部、もしくはある一側面を分析的かつ実直に捉えてそれを明文化することを得意とします。これら「感性」と「理性」は、どちらがどうというわけではなく、相互補完的に使い分けてゆくものだと私は思っています。(記事:伝える時には参照)ただ、人によっては感性でその主題を捉えているにも関わらず、それを論理化(もしくは明文化)できないということがあるということをお伝えしたいのです。人は感性で捉える時に、非言語的な知覚の仕方で対象から多くの印象を捉えています。なので、この感性が豊かな人程ことばで説明できない様々な考えをもっており、人に自分の考えを伝える事が苦手なものです。
これら感性豊かな人々の考えを生かしてゆくには、私たちが人と自分を比べて競い合うような競争心を持っていては難しいでしょう。理由を聞いてもすぐに答えられない相手を、無下に否定するのではなく、理由を一緒に探す手助けをしてあげたり、その相手の感性が捉えている「何か」を尊重してあげる姿勢が大切です。少し思い返せば誰にでも「理由は答えられないけどこう思う」といった考えを持った時があるのではないでしょうか。そうしたことを思えば、自分のその非論理的な考えに寄り添ってくれる人がいた場合どれだけ心強かったことか。私たちにそうした共存の意識があってこそ、そこにある感性は生かされてくるのではないでしょうか。人々が互いの異なった感性を認めて協力し合い、共存してゆく社会は素晴らしいものになると思います。