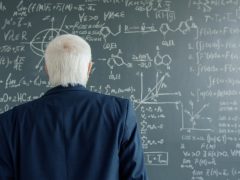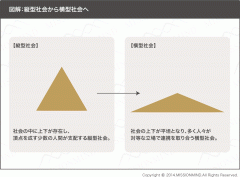伝える時には
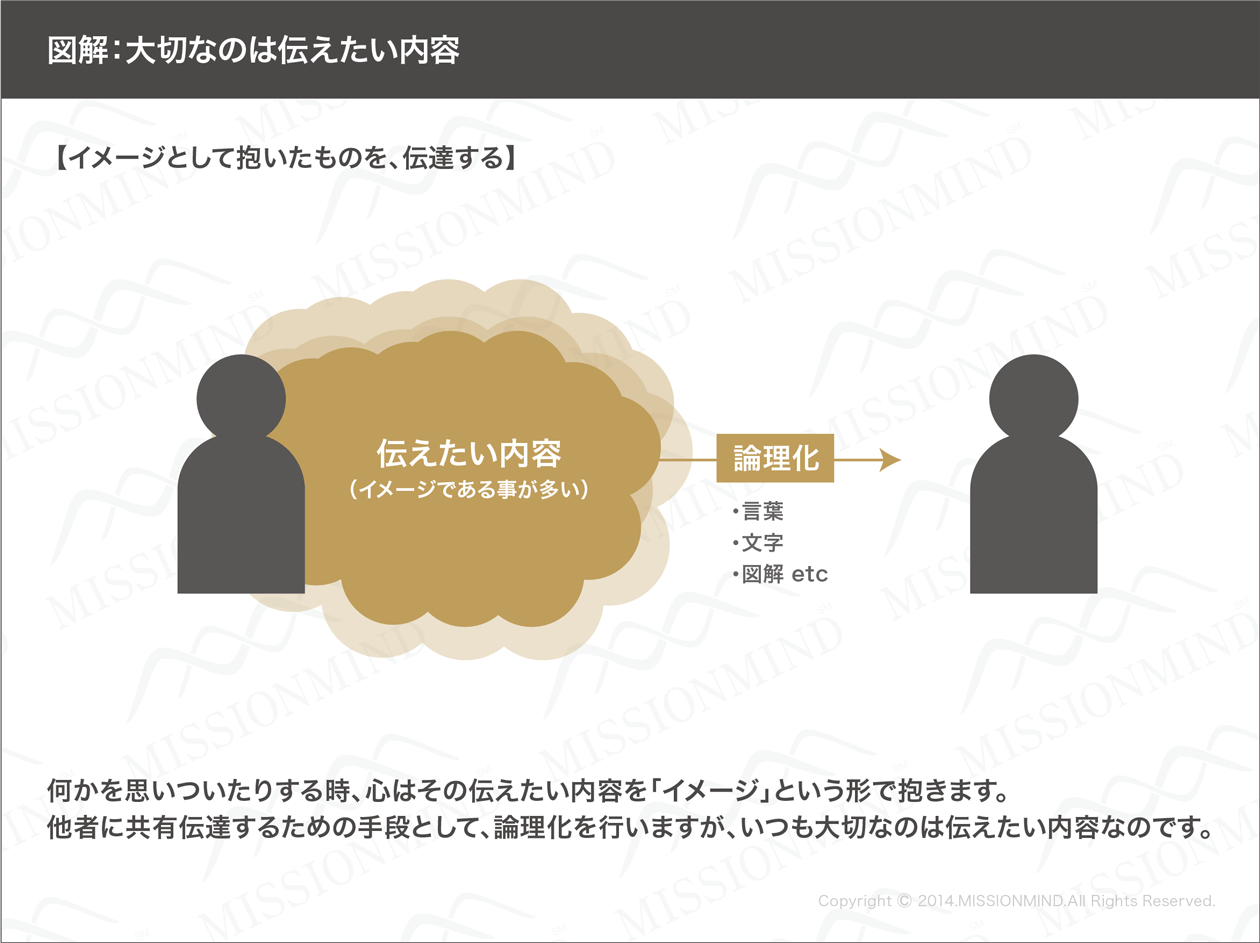
何かを伝えたり表現する時に、私たちは言葉や文字を使います。このMISSIONMINDでも、記事の中では文字や図解や写真を用いて、その伝えたい内容を表現しています。ここで重要なのは、言葉や文字そのものではなくて、伝えたい内容だったり、イメージの方なのです。私たちは、何かを思いついたり、それなりの主張を持つ時、心の中で「イメージ」としてそれを抱きます。それを伝えるための手段として、なるべく論理に筋を通して文字や言葉に置き換え、なるべくその構造を整理し、印象として全体が見えるように図解をしたり写真を付随したりするわけです。
このことは、私たちの他の日々の仕事の場でも、大切になってくる心持ちのように思います。何か新しい企画の「イメージ」を思いついたとして、それを伝えるためには企画書に落とし込む必要があり、その時に参考資料だとか、コンセプトだとか、利益計算だとか様々な題目に沿って論理を構築し、社内の人達に伝える必要が出てきます。これを仮に「論理化」と呼びます。
企画書ではじめに抱いたイメージを、論理化する過程では「自分は何を伝えたいのか/どういうイメージか」を見失わない事が大切になってきます。というのも、言葉に言葉を重ねてそれをさらに整理してゆこうとすると、当初のイメージが屈曲され、気付かぬうちにおかしな方向に不時着してしまうことがあるためです。これは文章に限らず、人との会話でも多くの人が経験した事があるのではないでしょうか。この時に、私たちは手段と目的をごっちゃにしてしまっているのです。ここでいう目的とは「伝えたい内容を伝えること」であり、論理化することはそれを他者に共有するための手段です。
私自身ここで記事を構文したり図解をしたりと、その他にも、仕事柄「伝える」ということの難しさを日々痛感しています。当初にあった伝えたい内容が、記事を書いてゆくうちに簡単にひっくり返ってしまうのです。このことを「なぜなんだろう」と考えたのが、この記事を書くキッカケとなりました。
たとえば「綺麗な形で表現しようとしすぎる」というのがあります。すでに出来上がっている文章で、その意図は伝わっているにもかかわらず、無闇に手を加えてしまう事で、逆にその核心を見えにくくしてしまうということです。文章的には当然綺麗になってゆきますが、それでは意味がないのですね。これは、自分への「もっとできるはずだ」という期待からくるものだと思います。この自分への期待自体は、自己成長に繋がるものなので素晴らしいものなのですが、あまりにその思いが強すぎるのも良くないというわけです。
他には「俯瞰的になりすぎる」ということもあります。自分が文章を書いているうちに、いつのまにかそのイメージを見下した目線となってしまい冷めた目線になっていってしまうのです。そのことで、文章自体は整理されるのですが、それにより伝えたかった思いや気持ちといった一番核となる部分だけがスッポリと抜け落ちてしまうのです。
これらは、企画書や構文などに限らず、対人関係の会話でも同様のことが言えるように思います。綺麗でなくてもいいのかもしれません。伝える時に大切な事はいつも「何が伝えたいのか」です。自分が「伝えたい事は何か」そのことをちゃんと見続けていられているか、それを考えてみるのも良いかもしれません。