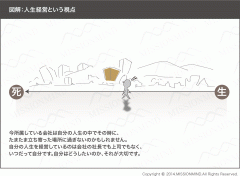ホリエモンは正しい。しかし足りない。
 人工的に作られたグルタミン酸ナトリウムと、自然に含まれるグルタミン酸ナトリウムは同じだ。ホリエモンがそう語ったとき、多くの人は、その通りだと受け取ったかもしれない。たしかに構造式としては、完全に一致している。理性の枠組みの中では、この発言は正しいし、疑いようがない。
人工的に作られたグルタミン酸ナトリウムと、自然に含まれるグルタミン酸ナトリウムは同じだ。ホリエモンがそう語ったとき、多くの人は、その通りだと受け取ったかもしれない。たしかに構造式としては、完全に一致している。理性の枠組みの中では、この発言は正しいし、疑いようがない。
しかし、この一言は現代が抱える「もう一つの層」をあぶり出す。それは、理性が掬い上げる世界と、感性が受け取る世界がしばしば異なるという事実である。どちらが優れている、どちらが正しいという話ではない。ただ、見ている「世界の階層」が違っているだけだ。
理性は世界を分解し、均質化し、情報に変換する。自然と人工を成分で判断するというのは、この合理的世界観の成果だ。科学が巨大な成功を収めてきたのは、この「抽象化の力」によってである。
だが、人間の感じている世界は、それだけでは説明できない。成分が同じであっても、私たちの身体は微妙な違いを鋭敏に感じ取っている。香りの立ち上がり、口に入れた時の気配、余韻として残る微細な揺らぎ、記憶が呼び起こされる瞬間。理性の世界では「誤差」に分類されるものが、感性の世界では「本質」として立ち上がる。
自然と人工の違いは、化学構造ではなく、太陽のリズム、土地の個性、微生物の営み、人の生活史・・。そうした無数の「関係性の層」そのものだ。身体はその痕跡を読み取り、リアリティとして受け取る。
このことを、阪大教授の村上靖彦氏は見事に次のように表現している。
論理的な構造が支配する完全な客観性の世界が自然科学において実現したとき、自然は実はそのままの姿で現れることをやめ、数値と式へと置き換えられてしまう。自然を探究したはずの自然科学は、自然が持つリアルな質感を手放すようになるだろう。雨や風の音や匂い、草木が繁茂していく生命力は消えていく。客観性の探究において、自然そのものは科学者の手からすり抜け、数学化された自然が科学者の手に残ったのだ。
まさに、理性と感性の断層を指し示す言葉である。
ホリエモンは理性的には正しいと思う。だが、世界は理性で説明できるほど単純ではない。そして、人間が生きる上で本当に重要な部分をすくい上げるのは、理性ではなく感性のほうだ。ホリエモンの主張には、その感性の領域がすっぽり抜け落ちている。そこが、彼の言葉がどれほど正しくても足りない理由である。
理性は秩序を整え、世界を説明し、共有可能にする。感性は、秩序が立ち上がる前の「生の現象」を拾い上げる。この二つは本来、対立するものではなく、補い合う両輪だ。
AIが理性的領域の多くを置き換えつつある今、人間に残されるのは「感じる力」である。美しさ、余白、違和感、気配、手触り、物語。数値化できない価値が、これからの中心になる。
ホリエモンの発言は、理性が築いてきた文明の終わりを告げるものではない。ただ、その先にある「感性の時代」への扉を静かに開くきっかけになる。
成分が同じなら同じ。それは理性の世界では正しい。しかし、世界は情報としてだけ存在しているのではない。世界は、揺らぎとしても、気配としても、物語としても存在している。
これから必要なのは、理性を捨てることではない。理性の隣に、もう一つの「感性の眼」を置くことだ。そのとき世界は初めて立体となり、私たち自身もまた、生きた存在として世界を感じはじめる。