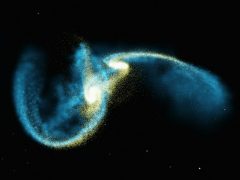理性から感性へ ~科学のまなざしから~
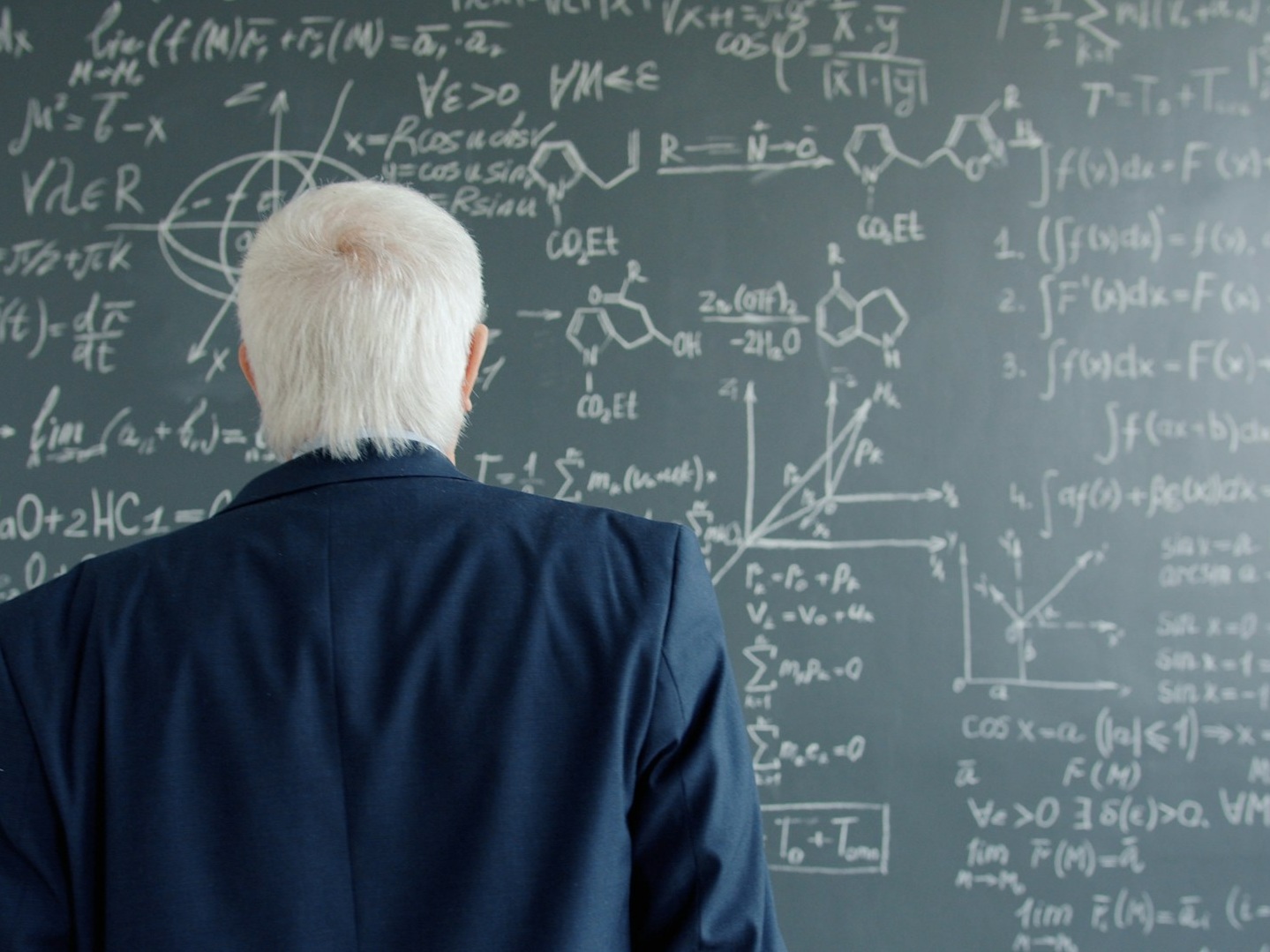 私はずっと前から、理性から感性の時代に移行していくのではないかと感じてきました。その理由を、科学の側面から少し考えてみたいと思います。
私はずっと前から、理性から感性の時代に移行していくのではないかと感じてきました。その理由を、科学の側面から少し考えてみたいと思います。
スティーヴン・ホーキングはこう述べています。
宇宙のすべてを丸ごといっぺんに説明する理論を考案するのは非常に困難であることは明らかです。私たちはその代わりに、問題を細かく分割し、部分的な理論を作り出してきました。これらそれぞれの部分的な理論は、観測された事実のうちある限られた事象についてのみ説明したり予測したりすることはできますが、それ以外の要素がもたらす影響は無視するか単純な数字として表します。
おそらくこのアプローチは完全な誤りでしょう。もし宇宙に存在するすべてがお互い根本的に依存しあっているならば、他と切り離して問題の一部のみを調べることで完全な解決策に近づくことは不可能なはずだからです。それにもかかわらず、私たちはこれまでこうした方法で進歩してきました。
この言葉には深く共感します。私もまた、全体を部分に切り分けて理解しようとする近代科学の方法に、どこか根本的な限界を感じてきました。人間は、世界をより正確に理解しようとするあまり、それを構成する要素を細かく分けて分析するようになりました。この「要素還元的アプローチ」は、物理学から生物学、経済学にいたるまで、近代文明の発展を支えてきた中心的な考え方です。しかし、そうした方法で扱えるのは、あくまで「他の影響を無視したときの世界」なのかもしれません。
もし宇宙のすべてが根本的に結びつき、互いに依存し合っているのだとしたら、部分を切り離して理解することは、ほんとうの意味での理解にはならないのではないでしょうか。存在は単独では成り立たず、常に「関係」として現れ、「関係」として消えていきます。私たちが生きているこの世界も、孤立した粒の集まりではなく、ひとつの大きな流れの中で生まれ、変化し続けているのだと思います。
こうした見方は、「構成論的アプローチ」あるいは「全体的アプローチ」と呼ばれます。それは要素を分けて理解するのではなく、つながりや関係そのものに意味を見出そうとする立場です。部分の総和では説明できない全体のふるまい、それが一般に「創発」と呼ばれます。宇宙の根源的な動きも、そうした創発の連なりとして見ていけるように思います。つまり、宇宙を理解するとは、海を分解して魚を調べることではなく、海と魚がともに現れるその「関係性」そのものに目を向けることなのかもしれません。
こうして考えていくと、科学のあり方そのものが、今、静かに転換点を迎えているのではないかと感じます。分離と分析の時代から、統合と共感の時代へ。客観性の追求から、関係性の理解へ。理性によって築かれた世界は、これから感性によって再びつながりを取り戻そうとしているように思えるのです。