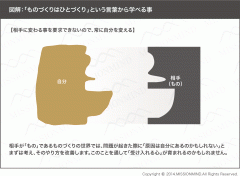理性から感性へ ~技術と人の新しい関係~
 私はずっと前から、理性から感性の時代がくると感じてきました。どうしてそう感じるのか。いろいろ思いつくのですが、今回は、技術の世界の側面から語ってみたいと思います。
私はずっと前から、理性から感性の時代がくると感じてきました。どうしてそう感じるのか。いろいろ思いつくのですが、今回は、技術の世界の側面から語ってみたいと思います。
2017年のことですが、私は大阪大学の石黒浩先生の講演を聴く機会がありました。石黒先生は、人と関わるロボットや人間酷似型ロボット(アンドロイド)の研究開発で知られる方です。その講演で先生はこう語っていました。
かつての製品開発は、機能だけ、つまり人間と切り離された機能にばかり注目していた。しかし基本的な機能は概ね研究が終わり、これからは「人間とのインターフェイス」の部分が重要になってくる。
私はこの言葉を聞いて、深く共感したことを覚えています。というのも、まさにその変化を私自身、さまざまな分野で感じていたからです。
わかりやすい例として、車を挙げてみたいと思います。私が若かったころは、テレビではF1レースや耐久レースが盛んに放送されていました。しかし今は、それらは継続して開催されているものの、以前ほど注目されていません。その理由は、メーカーごとの技術的な差がごくわずかになってしまったからではないでしょうか。
レースの勝敗を決めるのは、もはや車の性能よりもドライバーの技術や戦略によるところが大きい。そして、レースで勝ったからといって、ユーザーがそのメーカーを選ぶ理由には直結しません。どのメーカーの車も、市中を走るには十分すぎるほどの性能を備えているからです。
このことからも、すでにユーザーは車の性能だけで選んでいるわけではないことがわかります。いま求められているのは、性能ではなく「感性に響く魅力」です。つまり、石黒先生の言葉を借りれば、技術が「人間と切り離された世界」から、「人とのインターフェイスを意識した世界」へと変わりつつあるということです。
では、どうすれば人の感性に響かせることができるのか。マツダは「走る喜び」というコンセプトのもと、走ることそのものが楽しくなるような車をつくっています。それは単なる移動手段ではなく、走る行為そのものが感覚的な満足をもたらす車です。こうした試みは、理性の時代に生まれた技術を、人間の感性に結び直そうとする動きのひとつだと思います。
もちろん、もっと感性に響く車がこれからも誕生していくでしょう。メーカー各社はまだ模索の途中にあります。たとえば、四人で乗ることが楽しくて仕方がない車があってもいい。四人が一緒に乗れば、燃費は実質的に四倍になります。一見突飛に思えるかもしれませんが、こうした発想こそ、感性の時代にふさわしいものの見方ではないでしょうか。
人の感性に響く製品を開発していくには、これからは石黒先生のように「人間とのインターフェイス」に着目していくことが欠かせないと思います。石黒先生がつくるロボットは、完全な人間の模倣ではありません。むしろ、どこかに「ズレ」を残しています。けれども、そのわずかな違和感にこそ、私たちは強い「人間らしさ」を感じ取ります。
先生が本当に見ているのは、ロボットそのものではなく、ロボットを見つめる人間の反応です。その不完全な存在を通して、人間がどんな瞬間に「他者」を感じ、どんなときに「心のつながり」を覚えるのかを探っているのです。
こうした探求は、私たちの仕事にも共通していると思います。メーカーごとの技術的な差がこれからますます小さくなっていく中で、求められるのは理性によって積み上げてきた技術を、どのように人の感性と結びつけていくかということだと思います。性能を競う時代が終わり、これからは人が感じることが、技術の方向を決めていくようになる。私は、その流れの中にこそ、次の時代の豊かさがあると感じています。