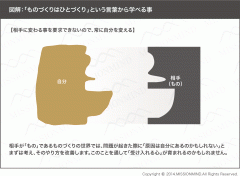世界は脳が作った像にすぎない
 私たちは世界を見ているのではない。脳が生成した像を「世界だ」と信じているだけだ。にもかかわらず、その事実を自覚して生きている人はほとんどいない。まるで自分が外界そのものを捉えているかのように錯覚している。
私たちは世界を見ているのではない。脳が生成した像を「世界だ」と信じているだけだ。にもかかわらず、その事実を自覚して生きている人はほとんどいない。まるで自分が外界そのものを捉えているかのように錯覚している。
チームラボの猪子寿之さんは、西洋の絵画は遠近法によって「視点を固定した世界」を描くのに対し、日本の絵画はそうではないと言った。日本の絵は、複数の視点・時間・空間が同時に存在する「超主観空間」であり、見るものと見られるものが溶け合っている。その話を聞いた瞬間、私は気づいたのだ。世界の「見え方」とは文化がつくったアルゴリズムであり、脳はそれに従って現実を合成しているにすぎない。
黄色い花があるとしよう。誰もが黄色と答えるだろう。しかし光の波に「黄色」は存在しない。黄色を生成しているのは脳だ。そして、その黄色は、生物としての普遍性ではなく、文化が共有してきた「こう見えるはずだ」という合意の上に構築されている。
つまり、脳の知覚アルゴリズムは個体に内在する固定的なプログラムではなく、文化や時代が長い時間をかけて脳に上書きしてきた「世界の作り方」でもある。
遠近法の発明以前、人類は「奥行きのある空間」をそもそも認識していなかった。古代ギリシア人は「青」の概念をほとんど持たず、海を「青い」とは認識していなかった。これらはすべて、世界の見え方は文化的アルゴリズムによって決まるという事実の証拠である。
だとすれば、古代の壁画が私たちには稚拙に見えても、当時の人々には十分リアルだった可能性が高い。彼らは私たちとはまったく異なるアルゴリズムで世界を合成していたのだ。「リアルとは何か」という問いそのものが、文化と脳の相互作用によって作られている。
しかし、私たちはこの構造にほとんど気づかない。なぜなら、脳はアルゴリズムの存在を隠蔽するように働くからだ。透明な水の中にいる魚が水を認識できないように、人は「自分の認識方式」を認識することができない。
そして現代では、西洋的な視点固定型のアルゴリズムが世界の標準となり、私たちの脳はその方式に合わせて世界を描くように訓練されてしまった。まるで、唯一無二の現実がそこにあるかのように。
しかし現実は逆だ。世界が一つなのではない。世界をつくるアルゴリズムが一つに揃えられただけだ。
本来、人間が世界を認識する方式はもっと多様だった。もっと揺らぎ、もっと曖昧で、もっと重層的で、世界と自分の境界はずっと薄かった。日本画のように、複数の時間と空間が同時に息づく世界が、本来の「人間の知覚」だったのかもしれない。
もし、脳が五感をどう合成するかが文化で変わるのだとしたら、私たちが「見ていると思い込んでいる世界」は、いかに人為的で、限定的で、歴史的に偏った認識の産物であるか。
私たちは世界を見てはいない。脳が描いた像を「世界だ」と信じているだけだ。そしてその描き方は、文化・時代・共有された物語によって絶えず書き換えられてきた。
世界とは外側にあるのではない。脳が選んだアルゴリズムの結果として「立ち上がる」現象なのだ。このことに気づいた瞬間、世界を見るとは「外界を知ること」ではなく、自分の認識そのものを知ることへと反転する。