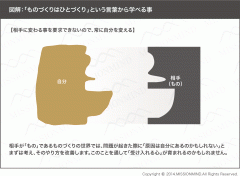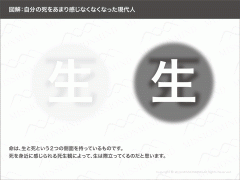宇宙のしくみ ~無と有のあいだ~ 第二章
 第2章 宇宙が自らを認識する仕組み
第2章 宇宙が自らを認識する仕組み
磁石を観察すると、内部から外部へ抜け、また戻ってくる連続した流れが存在しています。いわゆる磁束です。私たちは、この途切れない流れを直接見ることはできませんが、方向が変わる部分を通じて、その存在を「極」として感じ取っています。磁極とは、固定された実体ではなく、流れがつくる一時的な輪郭だと言えます。
この「流れと輪郭」という関係は、世界の見え方そのものを考えるうえで示唆的です。私たちが「ある」と感じているものは、静止した物体ではなく、背景に続く変化が一定の形をとった瞬間にすぎません。磁束の流れが輪郭を生み、輪郭が流れを際立たせるように、世界の多くの現象も、変化と形が互いを補い合いながら立ち上がっています。
こうした関係は、宇宙の広がりを理解するときにも役立ちます。私たちは、世界の出来事を一つひとつ切り分けて捉えがちですが、それぞれは単独で存在しているわけではありません。複数の動きが重なり合い、互いを照らすことで、はじめて意味のある姿が浮かび上がります。あるものが別のものを引き立て、その相互作用の中で新たな現れが生まれる。この重なりが、世界の多様さの源になっています。
観察という行為も、この関係と深くつながっています。私たちは対象をただ「眺めている」ように思いますが、実際には、観察することで対象の姿が変わり、自分自身の見え方もまた変化しています。見るとは、対象とのあいだに関係を結び、その関係の中で姿が定まっていく働きです。世界は、一方的に与えられる風景ではなく、関わりによって形を得る現象だと言えます。
完全な静けさだけが広がっていたと想像できる世界に、わずかな偏りや揺らぎが生まれることで、輪郭や動きが立ち上がります。その積み重ねが、のちに生命や社会や文化のような新しい現象を生み出してきました。個々の要素には存在しない性質が、全体の関わりによって突然現れることがあります。これが、私たちが「創発」と呼んでいる現象の土台になっています。
宇宙はこうした創発を繰り返し、自らの姿を更新しているように見えます。新しい構造が生まれるたびに、また別の出来事が生まれ、そのたびに世界の風景が広がっていきます。私たちが創造したり、誰かと出会ったり、新たな体験に触れたりするときも、世界の中に新しい輪郭が立ち上がる瞬間です。その一つひとつが、宇宙の中に新しい「感じられるもの」を増やしているのだと思います。
つづく・・・