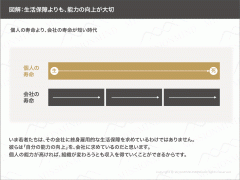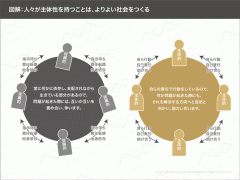和して同ぜず
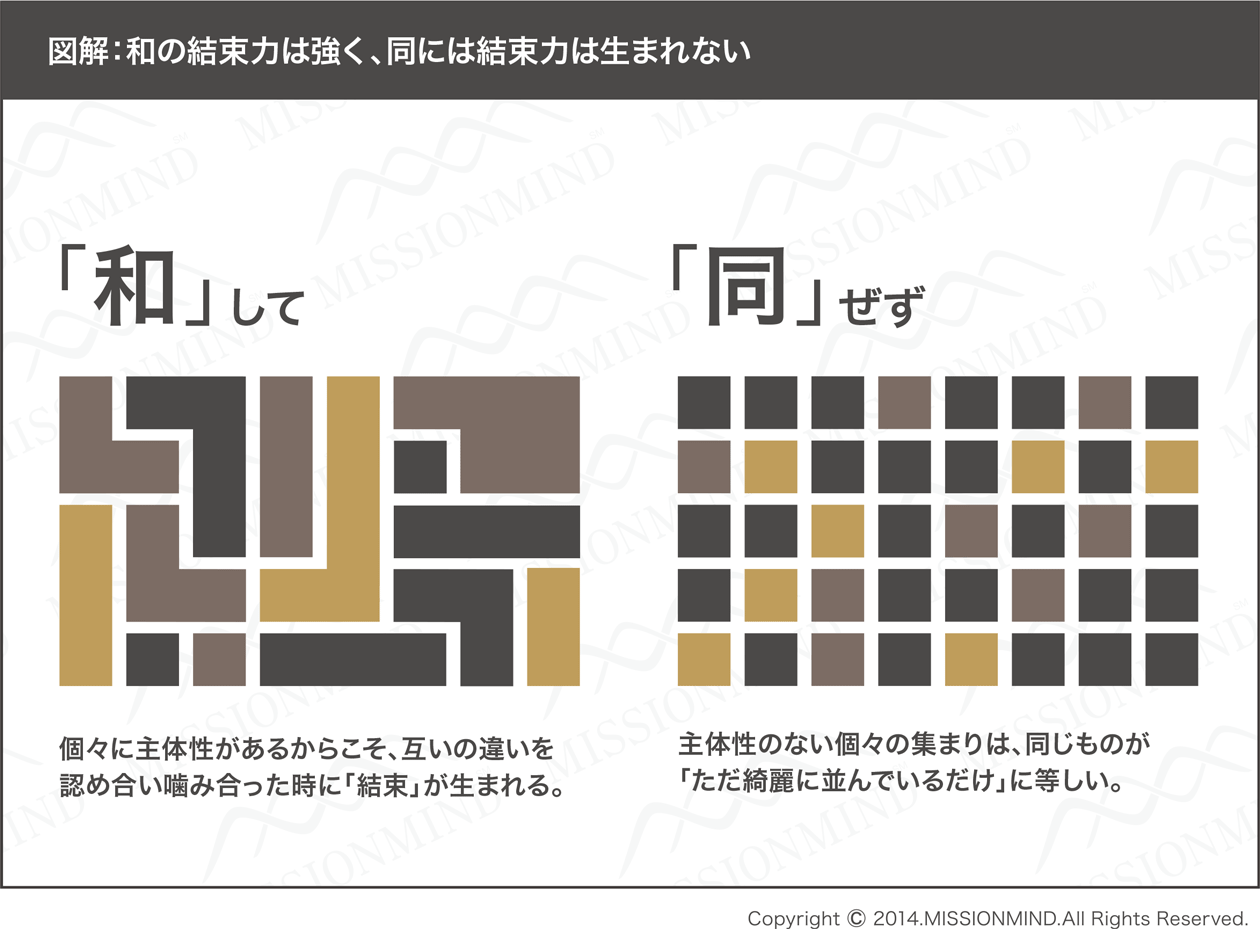
私は社員にセミナーに行ってもらうとき、いつも社員にお願いすることがあります。それは、自分の考えはこうだという主体性を持って聴いてほしいということです。もちろんそのセミナーを聴いているときは、とりあえず自分の考えは置いておいて、その講師のいうことを全面的に理解しようとする気持ちは大切です。でも、あとで振り返ってみたときに、その内容を何度も疑ってみてほしい。それこそが本当の理解につながると思うからです。
同じように、私が社員のみんなに話をするとき、私の話を盲目的に理解してほしいとは思っていません。それよりも、疑問をぶつけてくれてくれることのほうが、「考えてくれているのだなぁ」という気持ちになります。それに、私に「疑問をぶつけてほしい」という気持ちがなければ、いずれ会社はイエスマンばかりになってしまい、成長が止まってしまうでしょう。
「君子は和して同ぜず」という言葉があります。私は職場の「和」は大切に考えているけれど、「和」というのは、自分の考えを捨ててまで相手に合わせるという意味ではありません。それでは相手の意見に流されているだけの「同」になってしまいす。ほんとうの「和」というのは、主体性を持った上で相手の意見を受け入れるという意味だと思っています。各々が主体性を持っているからこそ、その違いが噛み合い理解し合った時にその結束力が強いものとなるのです。主体性のない「同」の結束力は結束というにはなんともか弱い「ただ同じ考えの人が集まっただけ」というような状況に陥りかねません。自分と周りとの「違い」を認め合い、結束し合う事が和なのです。
日本人は、世界の多様な文化を受け入れてきましたが、ただ受け入れるだけではなく、主体性を持った上で受け入れ、日本独自のものに変えてきました。もし受け入れるだけだったら、今日のような発展はなかったでしょう。日本人はあらゆる文化を融合し、独自のものに変えてしまう、天才的な能力を持った民族なのです。
いちばんそれを感じるのが、日本は西洋の全てを受け入れながら、その根本思想である宗教性までは受け入れなかったことです。無自覚であったのかも知れませんが、それこそが、これからの知識社会においては発展の原理となるでしょう。なぜなら、これからの知識社会においては「真理はひとつ」とする思想を持ったままでは発展することが困難だからです。あらゆる考え方を融合できる日本こそが、近い将来、世界文明の中心となる可能性を私は感じています。